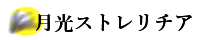表紙 > 本文
夜が明けたら 常本 雷遠
支度をする時間もなく、長い冬の夜が始まった。
この冬は、私の旅立ちでもある。
きっと、私は一人になる。誰も、何も、私とともに居てはくれない。
寂しさや不安のみが私を支配する。
私は、二度と戻れない家の鍵を閉めた。
行く当てなどどこにもない。
どこにいても、誰と居てもこの冬からは逃れられない。
誰もいない場所に行きたい。
そこでひっそり、一人で生きていきたい。
終わらない冬を、誰にも知られたくない。
けれど。
いつの間にか。こんなにも。
たくさんの人が、あらゆる場所にいる。
どこにも人のいない場所がなくなってしまった。
この冬に囚われた人間を、もう人間と呼んでもいいのかすら分からない私を隠してほしい。
親切から逃げ、優しさを振り払い、私は走った。
この冬が何なのか、私自身にも分からない。
いうなれば、この冬は恐怖とある種の羨望だろうか。
いつまでも変わることのない私を、最初は気にせず受け入れて。
いつからか、それが恐ろしいものであると気付かれ。
幾度も浴びた言葉がまた、異口同音に私を貫くのだ。
終わりのない冬は、私への罰だろうか。
何をかした記憶はない。記憶がないほどに些細な事として、大きな過ちを犯したのだろうか。
ならば、その罪とは何か。思い出せない。私は何をしたのか…そんなことも思い出せないのか……!
いつからか、私は私を責めていた。私自身に、疑心暗鬼になっていた。
もっとも信用のならないものを傍に置き、私は狂気に囚われていくと思った。
「あなたはきっと、私と同じものだ。信じられないなら、傍にいればいい。何百年でも、何千年でも」
狂気のみが彩る姿の私に向かい、穏やかにほほ笑む人が居た。
嘘だ。直感的に私の頭は否定し、逃げようとする。
しかし、私の体は、心は限界だった。
私の体は寄り添うように、その人の腕に吸い込まれていった。
あれから時がたった。それでも冬は終わらない。
私は未だ、囚われたままだ。
「おはよう。新聞持ってきたけど、読む?」
扉を開けて顔を出すのはあの人。
いつかまた、逃げねばならないだろうという恐怖は消えない。けれど、長きを共にしてくれている。
疑うことに疲れ、私はただ身を任せただけだった。
そのはずだったのに、この時間を大切に思う私に気付く。
終わらない冬。それでも夜は明けるのかもしれない。
「ありがとうございます。貴方は読まれましたか?」
不安と恐怖と、一筋の光を見て、私は立ち上がった。
-了-